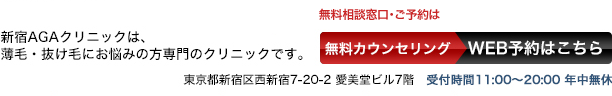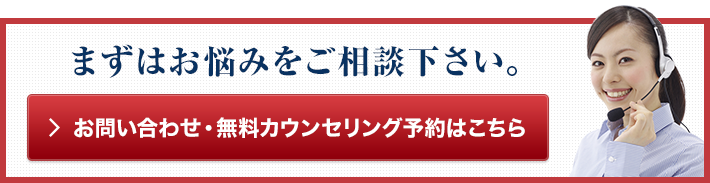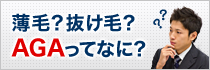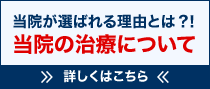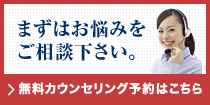頭皮のかさぶたをはがすのが危険な理由は?かさぶたができる原因や癖の治し方についても解説

かさぶたができるとついはがしてしまう方は多いのではないでしょうか。
かさぶたは血栓の一種で、何らかの原因で負った傷を治すためにできます。
頭皮は髪の毛に隠れて見えにくい箇所ですが、知らない内にかさぶたができているケースも珍しくありません。
頭皮にかさぶたができると気になってはがしてしまう方もいますが、さまざまなトラブルの原因となるため絶対に避けましょう。
こちらの記事では頭皮にかさぶたができる原因や、はがす癖を治すための方法などについて解説しています。
▽記事の内容をまとめた動画はこちら▽
目次
頭皮のかさぶたをはがすのは危険?
子どものころ、親や医師などからかさぶたをはがさないよう、注意された経験をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
では、頭皮のかさぶたをはがしてしまった場合、どのようなリスクが生じるのでしょうか。
頭皮のかさぶたをはがした場合、次のようなリスクが生じると考えられます。
- 細菌感染によって範囲が広がりやすくなる
- かさぶたをはがした跡が残りやすくなる
- 頭皮を傷つけてしまう
- 薄毛のきっかけになる
- AGA治療の妨げになる
そのため、かさぶたをはがす癖がある場合には注意が必要です。
それぞれのリスクについて、さらに詳しく解説します。
細菌感染によって範囲が広がりやすくなる
頭皮のかさぶたをはがした場合、細菌感染を起こして、かさぶたの範囲をさらに広げてしまう可能性があります。
そもそも、かさぶたは炎症が治まり、皮膚組織が再生されれば自然とはがれ落ちるものです。
ところが、無理にかさぶたをはがしてしまうと、再び傷口があらわれてしまいます。
手には無数の雑菌が付着しているため、傷口に触れることで細菌感染を起こし、かえってかさぶたの範囲を広げてしまう可能性があるのです。
どうしても無意識にはがしてしまう場合は専門医に相談しましょう。
かさぶたをはがした跡が残りやすくなる
頭皮のかさぶたをはがした場合、かさぶたをはがした跡が残りやすくなります。
かさぶたは傷口を治す過程でできるのですが、自然にはがれ落ちる前のかさぶたの下には傷口が残っています。
かさぶたをはがすと、はがしたかさぶたの下に、またかさぶたができることとなります。
そのようなことを繰り返しているうちに、徐々に傷口が深くなり、跡となって残るリスクが高くなるのです。
傷跡はそもそも次第に目立たなくなるものであり、完全に消えることはありません。
そのため、あえて傷口を広げることは絶対に避けましょう。
頭皮を傷つけてしまう
傷口の周りにある皮膚まで傷つけてしまうため、かさぶたを無理にはがすことは絶対に避けましょう。
特に指先や爪などでかさぶたをはがすと、かさぶたの端に付着している皮膚がはがれ、傷口を深くしたり傷の範囲を広げたりする恐れがあるため注意が必要です。
頭皮に傷が付くとシャンプーの際に傷口がしみて痛みを生じるだけでなく、紫外線など外部の刺激から皮膚を守ることができなくなります。
傷口が深くなるとズキズキとした痛みが生じ、ストレスの原因にもなるためかさぶたをはがすことは避けましょう。
薄毛のきっかけになる
薄毛のきっかけになる可能性もあるため、頭皮のかさぶたをはがさないよう注意する必要があります。
男性の薄毛の多くは遺伝的な要因によって発症の可能性が左右されますが、頭皮環境の悪化により抜け毛や薄毛のリスクを高めることもあることを知っておきましょう。
かさぶたをはがすと周囲の毛穴がふさがれるため、髪の毛の成長に悪影響をおよぼします。
また、かさぶたをはがすことで頭皮の炎症を引き起こすと、頭皮環境の悪化により抜け毛や薄毛のリスクを高める可能性があります。
AGA治療の妨げになる
AGA治療の妨げになる恐れもあるため、頭皮のかさぶたははがさないよう心がけましょう。
AGAは男性型脱毛症のことで、思春期以降に発症してゆっくりと進行する点が特徴です。
AGA自体は遺伝的な要因によって発症の可能性が左右されますが、かさぶたによって健康な髪の毛の成長が妨げられると、AGA治療の十分な効果が得られなくなります。
また、AGA治療薬の一種であるミノキシジル外用薬がかさぶたのために頭皮下へと浸透しにくくなる点も、AGA治療を妨げる要因の1つです。
頭皮にかさぶたができる原因は?
頭皮にかさぶたができる原因は、何らかの皮膚疾患を発症していることや体質など実に様々です。
そのため、自分の頭皮のかさぶたがなぜできているのかを知り、適切に対処することが重要です。
頭皮にかさぶたができる原因としては、主に以下のような例が挙げられます。
- 乾癬
- 脂漏性皮膚炎
- 白癬
- アトピー性皮膚炎
- ドライスキン
- ストレス
- 外傷
一口に頭皮のかさぶたと言っても、これだけのことが原因として考えられます。
それぞれの原因について詳しく見ていきましょう。
乾癬
乾癬(かんせん)は、炎症性角化症(えんしょうせいかくかしょう)に分類される皮膚疾患です。
名前からも分かるように、皮膚が炎症を起こし、皮膚の表面にある角層が分厚く角化して硬くなるのが特徴です。
また鱗屑(りんせつ)と呼ばれる、銀白色の細かいかさぶたがたくさんできるのも特徴で、乾燥したフケのようにぽろぽろとはがれ落ちます。
皮膚疾患の中でも難治性とされており、症状が軽減したかと思ったらまた悪化するといった経過を繰り返します。
脂漏性皮膚炎
脂漏性皮膚炎(しろうせいひふえん)は、皮膚に見られる炎症性の疾患です。
皮膚の常在菌の一種であるマラセチアが異常繁殖し、皮膚の炎症を起こすのが特徴です。
初期段階では痒みを感じないことも多く、気が付いたら進行していたというケースもあります。
どちらかというと、皮脂の分泌量が多い男性に多く見られる傾向があります。
白癬
白癬(はくせん)は感染性の皮膚疾患の一種で、皮膚糸状菌と呼ばれる真菌の一種に感染することで発症します。
代表的な白癬への感染症が、足に見られる水虫(足白癬)です。
頭に感染が見られる場合、頭部白癬や、しらくもなどと呼ばれることがあります。
頭部が白癬を起こした場合、頭皮にうろこ状のかさぶたを引き起こすことがあります。
また、まだら状に脱毛することもあります。
アトピー性皮膚炎
頭皮のかさぶたの原因としては、アトピー性皮膚炎も挙げられます。
アトピー性皮膚炎は、肘やひざの内側など、皮膚が柔らかい箇所にできやすいのですが、悪化すると全身に広がります。
アトピー性皮膚炎の特徴の1つが象皮症です。
象の皮膚のように皮膚が角質化して硬くなり、指先で掻くなどすると体液が漏出し、やがてかさぶたになります。
ドライスキン
ドライスキンも、頭皮にかさぶたができる原因の1つです。
ドライスキンはその名の通り、皮膚が乾燥した状態を意味します。
高齢者に多く見られる状態ですが、その他にも空気の乾燥や皮膚への摩擦刺激、紫外線、肌質に合っていないシャンプーや洗剤などが原因でドライスキンになることがあります。
痒みがあると無意識に引っ掻いてしまい、結果としてかさぶたが生じることもあります。
ストレス
意外に感じるかもしれませんが、ストレスも頭皮にかさぶたができる原因の1つです。
ストレス状態が昂じると、自律神経のうち交感神経が優位に傾きます。
交感神経が優位に傾くと、血管が収縮し、血液の循環が悪くなります。
それによって頭皮へ送られる血液量が減少すると、頭皮環境の悪化にともなって、かさぶたが生じるリスクを高めます。
外傷
頭皮にかさぶたができる原因としては、外傷も挙げられます。
外傷とは、外部から働く物理的、化学的、および機械的刺激によって、身体の組織が損壊されることを意味します。
転んで頭をぶつけたり、落下物が頭に当たったりすることで頭部に傷を負うと、傷口が治る過程でかさぶたが生じます。
無意識に引っ掻いてしまい、再びかさぶたとなるケースもすくなくありません。
洗い残し(すすぎ残し)
頭皮にかさぶたができる原因は皮膚疾患やケガだけでなく、日常の洗髪習慣にも潜んでいます。
例えばシャンプーやコンディショナーなどのすすぎ残しがあると、頭皮へ刺激を与える成分によって炎症を起こし、かきむしってかさぶたができるリスクを高めます。
また、十分に頭皮を洗えていないと、過剰な皮脂をエサとして頭皮の常在菌が繁殖し、かゆみを引き起こすことがあります。
そのため、毎日の洗髪を正しい方法で行うことが重要です。
頭皮のかさぶたをはがし続ける癖が付くのはなぜ?
頭皮のかさぶたをはがし続ける癖が付く主な理由は以下の2つです。
- かさぶたがかゆくてはがしてしまう
- かさぶたをはがすのが楽しい・気持ちいい
かさぶたがかゆくて剥がしてしまう方は皮膚疾患の可能性が、剥がすのが楽しい・気持ちいいと感じる方は皮膚むしり症の疑いがあります。
それぞれについて詳しく解説します。
かさぶたがかゆくてはがしてしまう
頭皮のかさぶたをはがし続ける癖が付く理由の1つが、かゆみを我慢できないためです。
かさぶたにともなうかゆみが出る原因について理解するためには、傷が治るメカニズムを知っておく必要があります。
- かさぶたができると病原体を除去するため免疫細胞の一種であるマクロファージが出動する
- 免疫細胞からのサインにより線維芽細胞が皮膚を再生する
- 皮膚の再生を促進するためヒスタミンにより血流が促進される
- ヒスタミンが神経の表面にある受容体と結合してかゆみが生じる
ヒスタミンはかさぶたを早く治すために欠かせない生理活性物質ですが、傷が治る過程でかゆみが生じやすくなります。
かゆみが生じると我慢できなくて、つい剥がしてしまう癖が付くケースが少なくありません。
かさぶたをはがすのが楽しい・気持ちいい
かさぶたをはがすのが楽しい・気持ちいいと感じることも、頭皮のかさぶたをはがし続ける癖が付く理由の1つです。
楽しい・気持ちいいなどの理由でかさぶたをはがす方は、皮膚むしり症を発症している可能性があります。
皮膚むしり症は強迫症の関連疾患に位置付けられており、皮膚をむしることで不安や緊張感などが和らぐ点が特徴です。
かさぶただけでなく健康な皮膚もむしるくせがある方は、皮膚むしり症も念頭に対処する必要があります。
頭皮のかさぶたをはがすのをやめたい!癖を治すにはどうしたらいい?
無意識にかさぶたをはがす場合、なぜはがしてしまうのか原因を突き止めることが重要です。
かさぶたをはがす癖を治す主な方法は以下のとおりです。
- かさぶたに触れない・はがさない
- 生活習慣を改善する
- 医療機関を受診する
かさぶたに触れない・はがさない
かさぶたに触れる必要がない、もしくははがす必要がないと考えることが、かさぶたをはがす癖を改善する結果につながります。
特に無意識にかさぶたをはがしてしまう方は、はがさないように意識することが欠かせません。
反対に、あえてかさぶたを探してはがしてしまう方は、かさぶたをはがすことのデメリットについて深く理解する必要があります。
何らかのストレスが原因でかさぶたをはがしてしまうようであれば、ストレスを根本から取り除くことも必要でしょう。
生活習慣を改善する
そもそも頭皮にかさぶたができなくすることが、かさぶたに触れないようにする一番の近道です。
例えば頭皮にかゆみがある場合、無意識にひっかいて傷つけてしまい、結果としてかさぶたができやすくなる可能性があります。
頭皮のかゆみは乾燥や肌質に合っていないシャンプー、皮脂の過剰な分泌などさまざまな原因によって起こります。
そのため、薬用シャンプーなどで優しく洗髪し、皮脂の過剰な分泌を促す脂質の多い食品を避けるなど工夫しましょう。
医療機関を受診する
セルフケアでは改善が見られない場合、医療機関を受診することが重要です。
かさぶたを早く治したいのであれば、皮膚科を受診するとよいでしょう。
皮膚科では炎症性の皮膚疾患全般の治療を行っています。
原因がストレスによるものであれば、精神科や心療内科を受診することがおすすめです。
精神科や心療内科では、なぜかさぶたをはがしてしまう原因を認知し、考え方や行動を変えていくための治療が行われます。
頭皮かさぶたを治す方法は?
頭皮のかさぶたは普段、髪の毛に隠れているため目立つことがありません。
ただ、かさぶたをはがしてしまうと、細菌感染を起こしたり、跡になって残ったりします。
そのため、頭皮のかさぶたに関しても、しっかりと治すといった発想が必要となります。
頭皮のかさぶたを治すためには、次のようなことを心がけましょう。
- 頭皮を掻きむしらない
- ストレスをためない
- 良質な睡眠をとる
- ヘアケア製品を見直す
- 医療機関を受診する
それぞれについて詳しく解説します。
頭皮を掻きむしらない
頭皮にできたかさぶたを治すためには、やたらと頭皮を掻きむしらないことが重要です。
頭皮のかさぶたは、頭皮にできた傷を治すためにできるものです。
ただ、傷が治る過程で炎症を生じた場合、痒みを伴うケースが少なくありません。
そのため、無意識に傷口を掻きむしって、かさぶたをはがす結果となるのです。
痒い所を掻くと、一時的な気持ちよさは得られますが、当然のことながら根本的な問題の改善には繋がりません。
むしろ、先述したように細菌感染を起こしたり、傷跡を残したりするリスクが高くなります。
無意識に頭皮を掻いてしまう場合は、爪を短く切りそろえて研ぐなどして、皮膚に外力が加わるのを避けましょう。
就寝時は、掻きむしりを予防する専用の手袋を履くなどするとよいでしょう。
ストレスをためない
ストレスをためないことも、頭皮のかさぶたを早く改善するためのポイントです。
ストレスがたまると自律神経のうち、交感神経が優位に傾き、血管の収縮および血行不良を引き起こしやすくなります。
血液は全身に酸素と栄養を運んでいますが、ストレスにより頭皮へ送られる血液の量が減少すると、かさぶたを治すための栄養が不足する結果につながりかねません。
ストレスを完全にシャットアウトすることは困難なため、自分なりのストレス解消法を実践しましょう。
良質な睡眠をとる
日常的に良質な睡眠をとることも、頭皮のかさぶたを治すためには欠かせません。
私たちの体内では夜間に成長ホルモンが分泌され、細胞分裂が活発化することで損傷部位の修復が行われます。
睡眠不足に陥ると成長ホルモンの分泌量が減少するため、かさぶたが治るまでに時間が掛かります。
良質の睡眠をとるためには普段から早寝早起きを心がけ、早朝の日差しを浴びて体内時計を調節することがおすすめです。
ヘアケア製品を見直す
頭皮にできたかさぶたを治すためには、普段使用しているヘアケア製品に関しても見直しの必要があります。
市販のシャンプーのなかには洗浄力が強すぎる商品があり、かさぶたがある際に使用するとさらにかゆみがひどくなる可能性があります。
洗浄力の強いシャンプーは頭皮を守るべき皮脂膜まで洗い流してしまい、外部の刺激に対して過敏になるため注意が必要です。
頭皮のかさぶたを治したい方は洗浄力のマイルドなアミノ酸系のシャンプーを使用するのがおすすめです。
また、乾燥は頭皮環境の悪化を招く恐れがあるため、頭皮専用のローションなどで保湿するよう意識しましょう。
医療機関を受診する
かさぶたを根本的に治すためには、かさぶたの原因となる疾患などを治療する必要があります。
アトピー性皮膚炎や脂漏性皮膚炎、白癬、乾癬などが原因となってかさぶたができるようであれば、原因となる疾患の治療を優先する必要があります。
また、アタマジラミやニキビなどが原因で頭皮にかさぶたができてしまう場合には、まずその原因に対する対処を行うことが求められます。
ニキビの場合は市販の頭皮用の治療薬を試す方法もありますが、アタマジラミの場合は専門家の診察を受けるようにしましょう。
かさぶたに伴って強い痒みがある場合や、フケのように皮膚がぽろぽろはがれ落ちる場合は、なるべく早めに専門医まで相談しましょう。
かさぶたができてははがすといった行為を繰り返していると、いつまでたってもかさぶたが治りません。
頭皮のかさぶたを予防・改善するためには?
頭皮のかさぶたを予防・改善するためには、正しいシャンプーの方法を身に付ける必要があります。
シャンプーは毎日のように行うものですが、場合によってはそれがかさぶたの原因となる可能性もあるからです。
正しいシャンプーのやり方は以下のとおりです。
- シャンプーの前にブラシで汚れを落とす
- シャンプーの前に予洗いをする
- シャンプーはお湯で伸ばしてから付ける
- 洗い残しがないようにしっかりとお湯で濯ぐ
頭を洗う場合、いきなりシャンプーをするのではなく、事前にブラッシングを行います。
ブラッシングすることで髪の毛に付着した汚れを落とし、染髪中に髪の毛が絡まりにくくなります。
シャンプーの前には予洗いをしましょう。
その後、手のひらでシャンプーを適度に伸ばし、何ヶ所かに分けて髪の毛につけ、指の腹で優しく洗います。
爪を立てて洗うとかさぶたの原因となるため避けましょう。
その後、洗い残しがないようしっかりとお湯で濯ぎます。
シャンプー後のドライヤーにも注意が必要
かさぶたを改善・予防するためには、シャンプーをした後のドライヤーにも注意が必要です。
早く乾かそうと頭から近い箇所でドライヤーを使ったり、熱風を地肌にかけ続けたりすると、かさぶたの原因となる頭皮の乾燥を招きます。
ドライヤーを使う時は、髪の毛や頭皮から15センチメートルほど離し、同じ箇所に風邪を送り続けないよう気をつけましょう。
また、手で髪の毛を持ち上げ、風の通り道を作ることで、髪の毛を早く乾かすことが可能です。
頭皮のかさぶたをはがす癖に関するFAQ
頭皮のかさぶたをはがす癖に関しては、以下5つの質問が多く寄せられています。
- 頭皮のかさぶたをはがす癖は薄毛の原因になる?
- 頭皮のかさぶたを放置すると髪が抜ける?
- 頭のかさぶたをはがし続けるとどうなる?
- 頭皮にかさぶたがある場合、美容院に行っても大丈夫?
- 頭皮のかさぶたをはがして荒れたら何科を受診すべき?
頭皮のかさぶたをはがす癖は薄毛の原因になる?
かさぶたを何度もくり返しはがしていると、薄毛の原因となる可能性があるため注意が必要です。
かさぶたを何度もはがしていると傷口の範囲が広がり、毛穴をふさいで髪の毛の成長を妨げる恐れがあります。
また、何度もかさぶたをはがすうちに傷口が深くなると、毛根に傷がつくなどしてヘアサイクルの周期を乱す可能性があります。
ヘアサイクルの回数には限りがあるため、ヘアサイクルの終わりを迎えた毛穴からは二度と髪の毛が生えてきません。
かさぶたが直接抜け毛を引き起こすわけではありませんが、頭皮環境の悪化が起こりやすくなるためはがすことは避けましょう。
頭皮のかさぶたを放置すると髪が抜ける?
頭皮のかさぶたは傷口を治すためにできる血栓の一種なので、放置したからと言って髪の毛が抜けることはありません。
しかし、かさぶたが何度もできるような場合、頭皮環境が悪化している可能性も疑われます。
頭皮環境が悪化するとヘアサイクルの成長期が短縮され、髪の毛を太く・強く成長させることができなくなります。
その結果として細く・弱い髪の毛が増えると、ちょっとした衝撃により抜け毛を引き起こすリスクが高くなるため注意が必要です。
頭のかさぶたをはがし続けるとどうなる?
頭のかさぶたをはがし続けると、次第に傷口の範囲が広がるだけでなく、ダメージが表皮だけではなく皮下組織や真皮にまで及ぶ可能性があります。
皮下組織や真皮にまでダメージが加わると、ターンオーバーの周期が乱れるため、頭皮環境が悪化してフケの量が増えたり、皮脂の分泌量が過剰になったりする可能性があります。
頭皮環境が悪化すると抜け毛のリスクを高めるだけでなく、皮膚炎を発症する可能性も高くなるため注意が必要です。
頭皮のかさぶたをはがす癖があっても美容院に行っても大丈夫?
頭皮のかさぶたをはがす癖があっても、美容院にカットをしに行くのは問題ありません。
かさぶたの原因であるドライスキンは男女ともに半数以上が自覚しているとのデータもあり、必ずしも珍しい症状ではありません。
むしろドライスキンに適したヘアケア製品の選び方や頭皮ケアのやり方などをアドバイスしてもらえる可能性があります。
乾癬や脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、白癬などが原因でかさぶたができている方は、美容院に行く前にかかりつけ医に相談してください。
特に頭部白癬は人から人に感染する恐れがあるため、マナーの上でも美容院側に知らせずに施術を受けるのは避けましょう。
頭皮のかさぶたをはがして荒れたら何科を受診すべき?
頭皮のかさぶたをはがして肌トラブルを引き起こした際には、皮膚科を受診するのが一般的です。
皮膚科では炎症性の皮膚疾患など、肌トラブル全般を扱っています。
しかし、心理的なストレスが原因でかさぶたをはがすようであれば、精神科や心療内科を受診して、原因を取り除くための治療を受ける必要があります。
頭皮のかさぶたにともなって抜け毛の量が増えている場合には、薄毛治療専門のクリニックを受診するとよいでしょう。
AGA治療に関するご相談なら新宿AGAクリニックへ
頭皮のかさぶたができるとかゆみを生じるケースがあり、剥がす癖が付く方も少なくありません。
かさぶただけでなく健康な肌も剥がしてしまう方は、強迫症の関連障害である皮膚むしり症の疑いがあります。
いずれにせよ原因を突き止めて適切に対処し、かさぶたをはがす癖をなるべく早くやめることが重要です。
かさぶたが直接的に抜け毛を引き起こす可能性は低いですが、頭皮環境が悪化するとAGA治療の妨げになる可能性があります。
頭皮のかさぶただけでなく抜け毛も気になる方は、新宿AGAクリニックの無料カウンセリングをご利用ください。

【 経歴 】
平成14年 大阪医科大学卒業
平成14年 大阪医科大学形成外科
平成16年 城山病院形成外科・美容外科
平成17年 大阪医科大学救急医療部(形成外科より出向)
平成18年 大手美容外科形成外科部長、多数の美容外科、形成外科で毛髪治療、植毛治療を経験
平成28年 新宿AGAクリニック院長
【 資格 】
日本美容外科学会専門医、日本麻酔科学会認定医、麻酔科標傍医、日本レーザー医学会認定医
«前へ「ヘアサイクルが乱れるのはなぜ?薄毛対策をするなら生活習慣を見直そう」 | 「亜鉛を取りすぎるとはげる?適切な摂取量や効果を解説!」次へ»