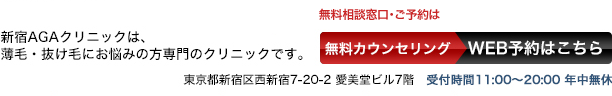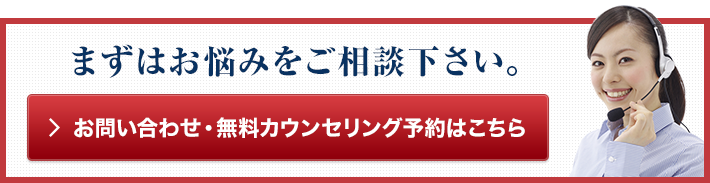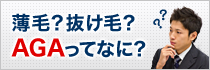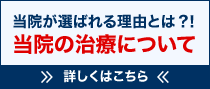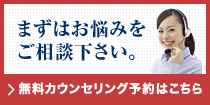円形脱毛症ガイドラインについて

診療科ごとに各医学学会が診療ガイドラインを作成しそれを参考にした診療が望まれています。
円形脱毛症(Alopecia Areata)の患者は少なはありません。病名は一般に広く知られていますが、病因が確立されていないことから正しい知識が普及しておらず、円形脱毛症に対する偏見など広範囲に脱毛する難治療の患者ではQOL(生活の質・生命の質)が低下するなど社会での生きずらさなどが問題となっています。
インターネットの普及により臨床結果に乏しい情報が氾濫し、誤った情報に患者が惑わされていた中で2010年
日本皮膚科学会が科学的根拠に基づいた標準的治療がはじめて提示され患者、医師双方にとって納得した治療を受けることができるよう策定されました。
脱毛症は加齢による変化や男性ホルモンによる男性型脱毛症、膠原病などの内蔵疾患や皮膚疾患に随伴する脱毛、薬剤性脱毛など医原性脱毛症などもあります。円形脱毛症を正しく理解し診断するために疾患概念、病因論、診断方法につての記述があります。
診断は毛髪の観察、牽引試験、爪の変形や問診の重要性があげられます。
病因については、毛包組織に対する自己免疫疾患を支持する論文を紹介し、
円形脱毛症を多因子遺伝疾患とされ、発症しやすい遺伝子を背景に、感染症などの肉体的、精神的ストレスが発症の誘因となるとされていますが明らかな誘因がない事が多いと示されています。
一般的に広く知られている円形脱毛症に対する原因の一つである精神的ストレスと円形脱毛症の発症に関しては項目を設けて記載されています。
その記述によると円形脱毛症と精神的ストレスとの直接の関連性についての科学的根拠は乏しく
安易に円形脱毛症とストレスの関与を伝えるべきではないとしています。
現在ストレスホルモンと毛包組織の関係についての研究が実施せれている事も紹介されています。
円形脱毛症治療ガイドラインの推奨度について

円形脱毛症の治療については29項目あげられており推奨度を検討しています。
新宿AGAクリニックでも行っております治療、
局所免疫療法はB(行うよう勧める)
セファランチン内服治療はC1(行ってよい)
ステロイド外用療法はB(行うよう勧める)
ステロイド局注療法はB(行うよう勧める)
ミノキシジル外用療法はC1(行ってよい)
また、当院では行っていない治療
ステロイド内服療法はC1(行ってよい)
静脈注射によるステロイドパルス療法はC1(行ってよい)
となっています。こちらの治療は副作用も多く、用いなくても当院では快方に向かうことが可能ですので行うことはないでしょう。
今回新しく設けられたものが【かつら】です。
かつらは円形脱毛症を治すものではないが円形脱毛症患者のQOLの向上に役立つとともに
当事者の中には生活に必要な方も多いことから推奨度は高くなっています。
行わない方がよいという項目も15項目記載があり、これらは根拠に乏しい治療が多数実施されていることを
示していると考えられます。
その中にPRP(Platelet rich plasma)療法も行ってはいけないという部類に記載があります。
なお、【治療をせず経過観察を行うのは有効なのか】という項目が設けられており患者に対し心理的配慮を行いつつ治療せず経過観察するという選択肢を提示してもよいとしています。
難治療である広範囲脱毛症において考慮されることと考えられるが、治療をあきらめるのではなく
積極的に治療しないことを患者自身が選び病気を受け入れ上手に付き合っていくという心理的な援助になると考えられたものです。
円形脱毛症ガイドラインの「その先」へ

現在、円形脱毛症の研究は急速に進んでおり海外で臨床試験が進行している新しい治療方法も存在します。
新宿AGAクリニックでは専門クリニックとして、海外の論文等で十分実績のある治療法について、円形脱毛症の治療ガイドラインの「その先の治療」を行っていっています。自費診療になってしまいますので、当然結果が伴うことは必須であると思っております。

【 経歴 】
平成14年 大阪医科大学卒業
平成14年 大阪医科大学形成外科
平成16年 城山病院形成外科・美容外科
平成17年 大阪医科大学救急医療部(形成外科より出向)
平成18年 大手美容外科形成外科部長、多数の美容外科、形成外科で毛髪治療、植毛治療を経験
平成28年 新宿AGAクリニック院長
【 資格 】
日本美容外科学会専門医、日本麻酔科学会認定医、麻酔科標傍医、日本レーザー医学会認定医