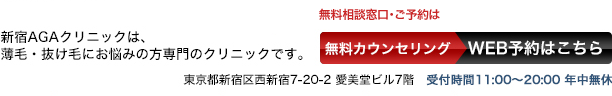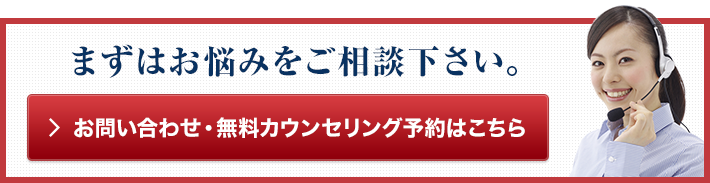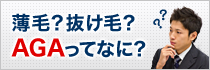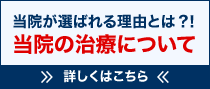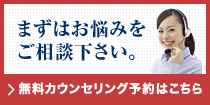生え際が薄い10~20代の人もいる?改善するために大切なこと

薄毛は頭部の様々な箇所にみられますが、生え際が薄くなることも珍しくありません。 生え際が薄くなると、他人の目が気になったり、将来的に薄毛のリスクが高まったりしているか可能性もあります。
しかし、前髪を下ろした髪型をしていると、生え際が薄くなっていることに気づきにくく、気が付いたら薄毛が進行していることも珍しくありません。 また、10代や20代の方であっても、生え際が薄くなることもあります。
この記事では、生え際が薄くなる原因や生え際の薄毛を改善する方法についてご紹介します。
目次
生まれつき生え際が薄い人はいる?
生え際の薄毛は、中高年以降になって目立つイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。 しかし、生まれつき生え際が薄いと感じる方もいるでしょう。
ここでは、生まれつき生え際が薄い人がいるのかどうか、という点について解説します。
生え際によっては薄く見える人もいる
生まれつき生え際が薄い人はほとんどいませんが、薄く見えるケースはあります。
生まれつき生え際がM字型になっている方の場合、生え際が薄く見えることがあります。 女性の場合、富士額(ふじびたい)といって、生え際が富士山の稜線のように、M字型になっていることもあります。 富士額と男性にみられるM字ハゲの違いとしては、M字の角度の違いが挙げられます。
富士額の場合は、M字の角度が緩やかであるのに対し、M字ハゲの場合はM字の角度が急である傾向がみられます。 また、富士額の場合は、生え際にしっかりとした髪の毛が生えていますが、M字ハゲの場合は、生え際部分の髪の毛が薄くなっています。
昔よりも生え際が目立つ場合は注意する
昔よりも額の広さが目立つようになってきている場合は、薄毛が進行している可能性もあるため、注意が必要です。
脱毛症を発症することで、富士額の部分が薄くなり、額が後退するケースもあります。 富士額であったり、生まれつき額が広かったりする場合は、生え際が後退しているわけではないため、心配する必要はないでしょう。
前髪を下ろしていると生え際を確認することができないので、定期的に鏡の前で前髪をかき上げ、額が後退していないかチェックすることが大切です。
生え際が薄い時に考えられる原因
ある日、鏡の前で前髪をかき上げた際、額が目立つようになっていたというケースも珍しくありません。
この場合、生え際が薄くなっている可能性があります。 生え際が薄くなる原因としては、主に以下のようなことが挙げられます。
ホルモンバランスが乱れている
生え際が薄くなってきている場合、ホルモンバランスの乱れが生じている可能性があります。
特に、女性の生え際が薄くなっている場合、ホルモンバランスに乱れが生じていることも多いです。 女性の髪の毛が男性に比べて豊かで艶やかであるのは、女性ホルモンの一種であるエストロゲンの働きによるものです。
ところが、出産後や更年期などにエストロゲンの分泌量が減少すると、髪の毛の成長が阻害され、結果として生え際が薄くなることがあります。
栄養が不足している
髪の毛に送られる栄養が不足していると、生え際が薄くなるリスクを高めます。
髪の毛が健康に育つためには、食事からバランス良く栄養を摂取する必要があります。 しかし、偏った食事や暴飲暴食など、食生活が乱れてくると、髪の毛の成長を阻害してしまう可能性があります。
また、女性の場合は過度のダイエットによって栄養失調が起こり、生え際部分の薄毛を引き起こすことがあります。
男性はAGAを発症しているケースもある
男性の生え際部分が薄くなっている場合、AGAを発症している可能性も疑われます。
AGAは男性型脱毛症と呼ばれており、思春期以降の男性であれば、誰でも発症する可能性があります。 AGAは、男性ホルモンの一種であるテストステロンが強力化し、ジヒドロテストステロン(DHT)へと変化することで発症リスクが高くなります。
ジヒドロテストステロンに変化する際に必要な5α-リダクターゼは、前頭部にも多く分布しています。 このため、AGAを発症すると生え際部分が薄くなってしまうのです。
生え際は10~20代でも薄くなる?
生え際が薄くなるのは、壮年期の男性や中高年以降の男性だけにみられる問題ではありません。
実際に、10~20代の方でも生え際が薄くなることもあります。 理由としては、以下のようなことが挙げられます。
遺伝の影響
10代~20代でも生え際が薄くなる理由として、遺伝の影響が挙げられます。
生え際が薄くなる原因の1つであるAGAは、遺伝によって発症するリスクも高いです。 このため、遺伝的にAGAを発症しやすい場合は、10〜20代の時でも生え際が薄くなることがあるのです。
過度なストレス
過度なストレスも、10代~20代で生え際が薄くなる可能性が高まります。
ストレス状態が継続すると、自律神経のバランスが乱れやすくなります。 自律神経のバランスが乱れると、血管が収縮して、血液の循環が悪くなります。
血液は全身に酸素と栄養を運んでいるため、頭皮へ送られる血液量が減少すると、髪の毛の成長に悪影響を与えるのです。
特に、頭皮には毛細血管が多く分布しているため、自律神経のバランスが乱れることで、栄養 を運ぶことが難しくなります。 また、生え際の薄毛自体がストレスとなり、さらに薄毛の進行を早める可能性もあるでしょう。
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れも、生え際が薄くなる原因の1つです。
暴飲暴食や偏食、過度のダイエットなどが原因で栄養バランスが偏ると、髪の毛が成長するためのエネルギーが不足します。 また、睡眠不足によって毛母細胞の分裂が阻害されると、髪の毛が十分に成長せず、細くて弱い髪の毛が増えてしまう可能性も高まります。
その他にも、運動不足や過労、不規則な生活などが原因となって血行不良や身体の回復力の低下を招き、生え際の薄毛を引き起こすこともあります。
生え際の薄毛を改善するために大切なこと
生え際の薄毛が気になると、それ自体がストレスとなり、さらに薄毛の進行を早める可能性があります。
このような事態を避けるためにも、適切な対策を講じることが大切です。 生え際の薄毛を改善するために大切な点をご紹介します。
正しくシャンプーを行う
生え際の薄毛が気になる場合、正しくシャンプーを行うことが大切です。
シャンプーは毎日のように行うものであるため、シャンプーのやり方が間違っていると、生え際の薄毛のリスクを高めてしまいます。 まず、シャンプーをする前に38度程度のぬるま湯で、しっかりと頭皮や髪の毛を洗います。
お湯が熱すぎると、頭皮を守るべき皮脂まで洗い流してしまうため注意が必要です。 シャンプーはいきなり髪の毛や地肌に付けるのではなく、いったん手のひらに乗せ、ぬるま湯で伸ばした上で、数ヶ所に分けて付けるようにしましょう。
頭皮は指の腹で優しくマッサージするように洗い、シャンプーが残らないよう、しっかりと洗い流すことが大切です。
質の良い睡眠をとる
質の良い睡眠をとることも大切です。
体内では、就寝してしばらくすると成長ホルモンの分泌が始まります。 成長ホルモンの分泌によって、細胞分裂が活発化し、損傷部位の修復が行われたり、身体の回復力を高めたりします。 髪の毛も毛母細胞の分裂によって成長するため、質の良い睡眠をとることが、生え際の薄毛の対策になります。
質の良い睡眠をとるためには、できるだけ早寝早起きを心がけ、しっかりと朝日を浴びることが重要です。
食生活を見直す
食生活の乱れは生え際の薄毛を招く可能性があるため、日々の食生活を見直すことが重要です。
髪の毛はタンパク質の一種であるケラチンから作られるため、良質のタンパク質を摂取するよう意識しましょう。 体内に入ったタンパク質はいったんアミノ酸に分解され、その後、ケラチンへと再合成されます。その際に必要となる栄養素が、必須ミネラルの一種でもある亜鉛です。
亜鉛は、ホウレンソウやレバー、牡蠣などに多く含まれるため、普段から意識的に摂取するように心がけましょう。 また、血行を促進したり、皮膚の新陳代謝を促したりするため、野菜や果物から、しっかりとビタミンを摂取することも重要です。
専門のクリニックを受診する
自分で対策をしても生え際の薄毛が改善しない場合、できるだけ早めに専門のクリニックを受診することが大切です。
男性にみられるAGAの発症が疑われる場合、徐々に薄毛が進行します。 AGAは前頭部や頭頂部から始まることが多いため、生え際の薄毛が気になりだしたら、AGAの発症を疑い、専門医に相談することが大切です。
生え際の薄毛に関するご相談は
生え際の薄毛は、男性だけでなく女性にもみられます。
また、壮年期から中年期の男性だけでなく、10代~20代の方にも起きる可能性があります。 特に男性の場合、AGAの発症に伴って生え際の薄毛が起こっていることがあります。 このため、できるだけ早めに治療を開始することが大切です。
新宿AGAクリニックでは、プロペシアやザガーロといったAGAの治療薬を処方しているだけでなく、女性でも受けられるメソセラピーという成長因子注入療法も行っています。 無料カウンセリングも行っておりますので、生え際の薄毛に関するお悩みなど、お気軽にご相談ください。

【 経歴 】
平成14年 大阪医科大学卒業
平成14年 大阪医科大学形成外科
平成16年 城山病院形成外科・美容外科
平成17年 大阪医科大学救急医療部(形成外科より出向)
平成18年 大手美容外科形成外科部長、多数の美容外科、形成外科で毛髪治療、植毛治療を経験
平成28年 新宿AGAクリニック院長
【 資格 】
日本美容外科学会専門医、日本麻酔科学会認定医、麻酔科標傍医、日本レーザー医学会認定医
«前へ「初期脱毛が終わる兆候はある?症状がひどい場合の対処法を解説」 | 「【医師監修】頭皮が硬い原因とは?硬くなるとはげる可能性がある?」次へ»